右足の靴を左手で、左足の靴を右手で脱がし、僕は裸足で大地に足を付いた。
真昼の太陽から受け取ったアスファルトからの熱が、僕の足の裏を通して伝わってくる。
太陽の熱が、僕の体温へと変わっていくのだ。
時刻はまだ帰宅ラッシュと呼ぶには早く、駅前は学生たちの話し声や車の喧騒で溢れていた。
これから刻々と、駅前は騒音に満たされていくに違いない。
僕は、この中途半端な時間帯が好きだった。昼と夕方の間の時間とでも呼べばいいのだろうか。学生たちにとっての、放課後という時間である。
左右の手にチグハグの靴を持ったまま、僕は駅前の噴水に向かって歩き出す。
一歩一歩、足の裏で小石や砂利の感触を味わいながら、噴水の前まで来ると、立ち止まった。
周りの目なんて気にしない。
ここには僕しかいないのだ、なんて錯覚を抱いてしまう。
この時間は、僕一人のものだ。
独占欲を満たす瞬間である。
この街は、この空間は、この世界は、すべて僕のものだ。
そんな満足感をたらふく飲み込むように、両手を広げて深呼吸をする。
ひんやりとした夕刻の空気が、肺の中に充満する。
世界と一つになる感覚を覚えながら、僕は空を仰いだ。
日が傾き始め、世界は赤く染められようとしていた。
来てよかった。
そんな達成感を抱きながら、噴水のそばにあるベンチの中央に、堂々とした態度で腰を下ろした。
浅く座り、そのまま脚を組んだ。ふと足の裏に目をやると、小さな砂利が皮膚にめり込むようにくっ付いていた。
それを指で取ろうかどうか考えていた時だ。
「やっと見つけました」
突然の声に、僕は驚いて顔を上げた。
ベンチに腰掛ける僕を見下ろしていたのは、一人の女性だった。
すらりとした細身の女性は、自分と同じくらいの二十歳くらいだろうか。
肩よりも少し長いくらいの黒髪が、夕陽の赤色を反射していた。
くりっとしていて少し垂れ気味の目が優しい印象を与え、ほんのりお化粧が乗っており、かわいいなって思ったのが第一印象であった。
彼女は、子供を見ているようなやさしい笑顔を浮かべ、今、僕を見ている。
彼女の真っ黒な瞳は、まるで鏡のように僕の姿を反射しているようだ。彼女はじっと、僕の姿を見つめている。
小さな瞳の中に、本当に自分の姿を確認したわけではないのだとは思う。僕も、それくらい彼女に魅入ってしまっていたのだ。
あの、何か用ですか。
「やっとお会いできましたね、こんにちは」
僕が訊こうとしたのだが、先に口を開いたのは彼女の方だった。
耳の奥にすぅっと染み込んでいくような明るくて少し高めの声が、聞いていて心地のいい声だった。その声質には喜びが含まれているのを感じ取ることができた。
そして、やはり嬉しそうに、彼女はこう言ったのだ。
「あなたが、この街に幸せを運んでくるという、黒猫さんですね」
にこりとした笑顔が眩しかった。眩しかったのは、彼女の後ろにある夕陽のせいかもしれない。
しかし、言っている内容は、僕には全く理解できなかった。
「いや、あんた、何言って」
「はい、これ」
困惑して訊き返そうとする僕にはお構いなしに、彼女は僕に向かって黒い何かを両手でぐいっと突き出してきた。
「これって」
僕は思わず立ち上がっていた。
彼女が手渡してきた物、それは、一足の黒い長靴だった。
サイズが明らかに男物で、工事業者の人が履いているようなシンプルな黒い長靴。彼女が身につけていたものではないことは明白であった。
長靴に向けていた視線を、彼女の方へ戻した。
彼女はまるで子供のように無邪気な笑顔を浮かべている。そして、
「これで、私を幸せにしてください」
なんていうお願いを口にした。
彼女の後ろに、先日開花したばかりの桜の花が咲いているのが見えた。
僕の背後では、噴水の水の音が聞こえる。
意味がわからない。
混乱しかしていない僕の内心をわかっているのかどうかはわからない。
彼女は子猫のような笑顔をこちらに向け、少し首を傾げながら僕の顔を覗きこんできた。
つづく。
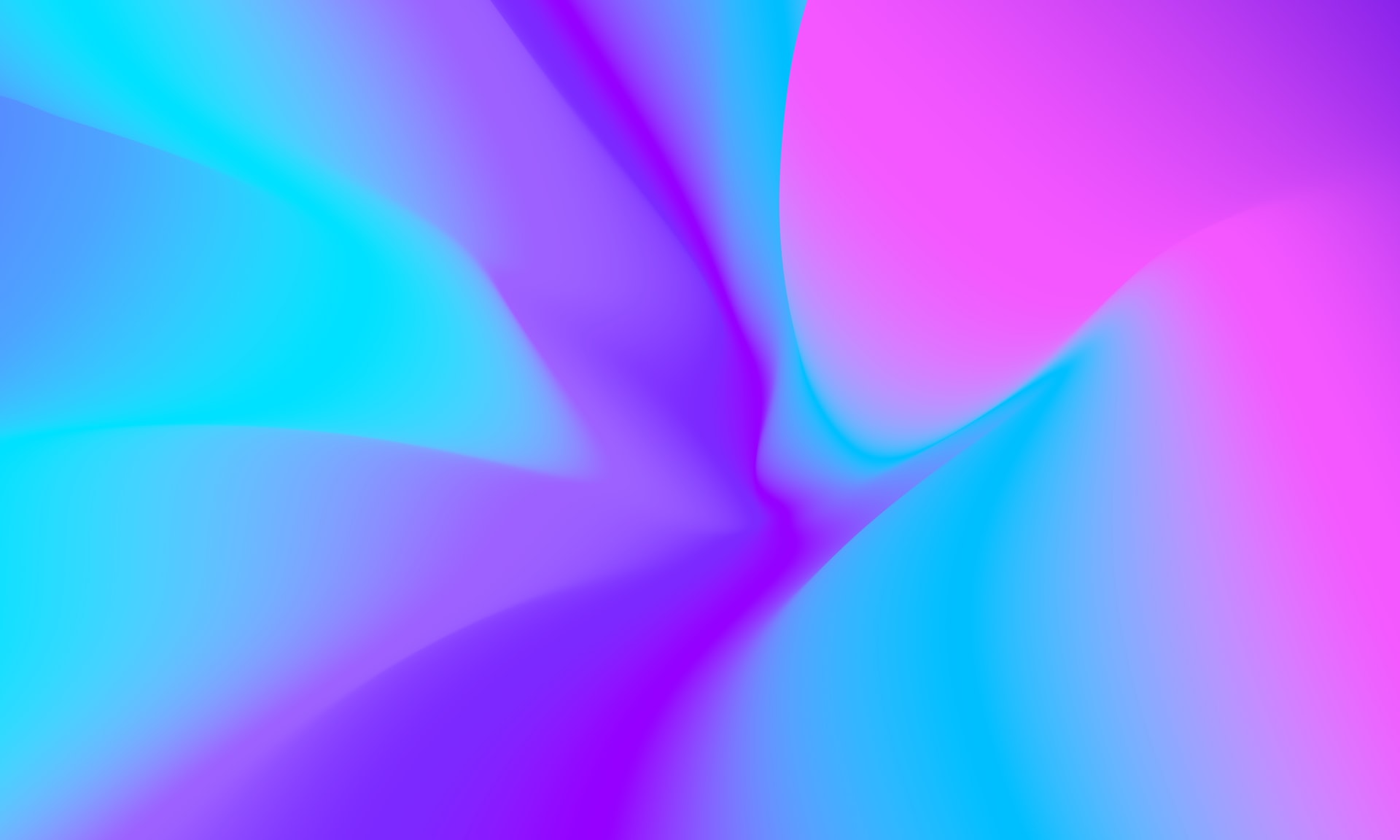


コメント