おはようございます! いずみちひろです。
本日は、先日に引き続き、自作品である”透明色の世界”の紹介です!!!
死にたがりの少女がビルから飛び降りたその下には――
死にたがりの少年との邂逅があった!!!
そんなストーリーです!!
これはたしか、大学4年のときにどこかのラノベの賞に送った作品を修正した作品です。
新人賞選考のバイトの方から、
「死をテーマにしてるわりには軽い」
とか、
「読者ターゲットがわからない」
などと、大絶賛されました!!!←
それもそのはず!!!
当時の自分は、
かわいい女の子を書きたい!!!!!
ただその一心で書きなぐってましたから!!!!!←ォィ
もちろん、書きたかったのはこの作品のヒロインである長崎志乃ちゃんです!!!
ちなみに、この作品のキャラの名前は長崎県の地名から持ってきてます(余談)
そして、この作品は製作にあたって、普段とは違う書き方を試みてみた作品でもあります。
だいたいの作品においては、まずプロットを書き、それなりに最後までのストーリー展開を頭の中で構築した後に、実際筆を走らせて書き起こす――って書き方が自分のスタイルだったわけですが。
この作品では、まず最初に全部会話文を書き出しました。
ストーリーなんて関係ありません、頭の中で話しかけてくる長崎志乃ちゃんのセリフを全て聴きながら、それをメモして書き起こすという手法で行ったのです。
そして出来上がったら、こんなことに……orz
昔話を語り始めたらきりがないのでこのへんにしておきますw
----------(ここから本編開始)----------
*
少女が夜空を仰ぐと、月が世界を見下して笑っていた。雲一つない快晴であるためその笑顔の邪魔をするものは、この世界にはどこにも存在しない。月は笑っていた。
やっぱり、あなたはうつくしいわ。
少女は天の笑顔に微笑み返しながら心の中で呟く。その心は嫉妬だった。
深夜二時を過ぎ営業時間を終えたショッピングセンターの屋上駐車場に、ひとり佇む少女の姿があった。他に人影はない。彼女は、独りぼっちなのだ。
白いワンピース姿の少女は転落を防止するための壁の上に立っていた。目下に広がる数メートル下にある世界をただ見つめていた。
下方では街灯の明かりの照らす所だけが闇から浮かび上がっている。
もっと高い所から地上を見渡したらきっと、夜空の星のように綺麗なんだろうな、と少女は思った。
すると、一際強い風が勢いよく屋上を通り過ぎていく。その風は、少女がこれから行おうとしている行為を思い止まらせようとしているような、そんな強さだった。
ワンピースの膝丈の裾が泳ぐように揺れたが、すぐにまた落ち着きを取り戻す。
風が通り過ぎた前と後とで、少女の決心は変わることはなかった。
少女は、じりっ、と右足をわずかに前へ引きずった。
爪先が、虚空に触れる。
大丈夫よ……初めてではないでしょ?
少女はそう心の中の自分に話し掛けた。
手に平には薄らと汗が滲んでいた。
私はこの世界に必要のない存在……そんな私がこの世界ですべきことは、一つしかないの。
胸の奥で、必死に、決意の火を灯そうとする。
寸前で臆病風に吹かれることも、初めてではなかった。
その行為を実行する前に、少女はもう一度だけ天を仰ぎ見た。
少女の頭上では――
やはり、月が笑っていた。
少女はゆっくりと左足を前へ引きずった。
踵だけで、少女は世界に立つ。
さようなら、世界――
少女は目を閉じた。
そして――
少女は、地上の星空の中へと、その身を投じた。
第一章 シノケッショウ
*
死とは、そこら中に散らばっているものなんだと思う。
目には見えないけれど、死とは形の美しい結晶のようなもので、この世界の至る所に、気づかぬ所に、たくさん落ちているものなのだ。
だけど、生きている人々は落ちている死の結晶に気づきもせず、時にはそれを上手くかわしながら、このくだらない毎日を生活している。
人々は知らないうちに死を拒み、回避しているのである。
だが、俺は違った。
俺は探しているのだ。
俺は死を見つけたい。
俺は死を手に入れたい。
要するに――
俺は死にたいのだ。
世界は死の結晶で満ちている。溢れるほどたくさん。
そのうちの一粒を、俺は欲しているのだ。
いつの間にか深夜の街を徘徊することが俺の生きがいとなっていた。
日の当たる昼間より青白い月光を浴びる深夜の方が死の結晶はより美しく輝いているはずだと、そう思ったから。
強い風が吹いた。
その風に俺は身を縮める。
秋の夜はいつの間にか肌寒いものへと変わってしまっていた。いつまでも夏気分が抜けきれない俺は今日も薄着だった。
今日も早く帰ることになるのかもしれないな……。
昨日の経験を生かしきれなかったことにより今日も寒さに耐えながら誰もいなくなった町をただ歩き続けた。
深夜の街を歩きながら俺は今日も変わり映えのしない景色を眺めている。
闇が深い所と街灯で薄まった所がある。本来闇が支配するはずの時間帯であるのに、人間の強欲で闇が虐げられているのだ。それはとても胸くそ悪い光景だった。
時計を見ると午前二時を過ぎていた。そろそろ帰って寝ないと明日の学校が辛くなる。
俺は今いるショッピングセンターの前で引き返すことにした。二階建てで外装はピンク色に近い色をしていた。屋上は駐車場になっている。田舎な町であるこの辺では大きい部類に入る立派な建物だった。
身を縮め、半袖でむき出しになっている腕をさすりながら、回れ右をした――
その時だった。
振り返った瞬間、目の前を真っ黒い何かが縦に横切った。空から何かが落ちてきたのだ。
目前を縦によぎったそれは、地面に叩きつけられて鈍い音を立てた。
俺は驚いた反射で目を閉ざしてしまった。
もう少しで直撃して、もしかしたら死ねていたかもしれないのに……、そんな考えが頭をよぎったのは、わずかに時間が過ぎ去ってからだった。
死の結晶はいつも、俺が手につかむ前に粉々に砕け散ってしまう。
ある程度落ち着いてきた俺は、暗いなか目を凝らしながら落ちてきたものが何なのかを確認した。
空から落ちてきた者――それは、ひとりの少女だった。
たった今目撃したこの光景は、映画などで見るワンシーンとは大きくかけ離れたものであった。
少女は血まみれだった。
おそらく初めは白かったのであろうワンピースは、赤と白の比率が逆転していた。血で染まったところは闇に飲み込まれており、白を保てた生地の部分は、月明かりを反射して淡く不気味に光っていた。
空から女の子が、と大騒ぎしていられる状況は少なくともこの場所には存在していなかった。
俺は事態に混乱しながらも、血塗れの少女に声を掛けた。
「だっ、大丈夫ですか?」
大きな声で少女に呼びかけてみるが返事はない。おそらくショッピングセンターの屋上から飛び降りたのだろう。
「もしもーし!」
夜の空っぽな町中に俺の大声が響く。もしかしたら、この声を聞きつけて誰かがやってくるかもしれない。その方がよかった。俺ひとりでこの場を対処するには、荷が重過ぎる。
三度目の呼びかけに、少女は反応を見せた。少女は死んでいない。
「もしもし、大丈夫ですか!」
俺は安堵しながらも、肝心なことを忘れていたことに気が付いた。
救急車を呼ばなくてはいけない。
「今救急車を呼びますから」
俺は震えて言うこと聞かない手を何とか動かして、ポケットから携帯電話を取り出した。折りたたみ式のそれを開きボタンを押そうとするが、ボタンが小さすぎてわずらわしい。焦りがさらなる焦りを呼んで、俺の手はがくがくと震え始めた。
「呼ばないで」
傷だらけの少女が口を開いた。
その言葉に、俺は目を見張った。
「呼ばないで」
少女は繰り返した。血のりで右目を覆われた少女は、左目だけで俺を見ている。ぼんやりと、瞳が淡い光を放っていた。その光は今にも消えてしまいそうなくらいの弱い光である。
自殺しようとして失敗したんだ。だからこのまま死ねたらいいと考えているに違いない。
俺にはすぐにピンと来た。。
少女は力無く呟くように言った。
「ダメ……私はここで死ぬの……それとも……あなたは私の……最期の勇気を……無駄にする気……?」
思ったとおりだった。
少女は、俺と同じ死にたがりだったのだ。
しかし、
「悪いけど――」
俺は携帯電話を片手に少女に言った。
今の状況に全然似合っていない少女の強気な瞳と、俺の瞳がかち見合う。
不謹慎だけど、少しタイプかもしれない。血まみれだけど、彼女は可愛かった。
俺は首を左右に大きく振って雑念をふり払う。
「悪いけど俺は他人の死にはまったく興味がない。だから、君を放っておくわけにはいかない」
俺は少女にそう告げると119を押して救急車を呼んだ。
電話がつながり場所と俺の名前を聞かれたので正直に答え、電話を切る。
数分で到着するらしい。
俺は少女を見た。
切れ長の目が俺を睨んでいた。
「……バカ」
少女の声はとても小さかったけれど、風が上手く運んでくれて俺の耳にまで届いた。
「バカで結構」
携帯画面を確認するともうすぐ二時半を回ろうとしていた。明日の学校は絶望的だった。遅刻せずにいける気がしない。
「はぁーっ、まったく。明日は遅刻だな、これは」
俺はこの場の空気の悪さを変えようと、軽いノリの言葉を発した。
そして、ちらりと少女を横目で見やった。
少女はまだ俺のことを睨んでいた。
俺は慌てて目を逸らす。
「……バカ」
少女が再び俺の悪口を言うが、今度は聞こえない振りをした。
サイレンが近づいてくる。夜の静かな空気をビリビリ揺らしながら、不愉快な音が大きくなっていく。
音が最音量を向かえ、一気にゼロになると、救急車が俺たちの前で停車した。
少女が車内に運び込まれ、俺は後を追うように中に乗り込む。
サイレンを鳴らしながら、救急車は病院へと向かった。
これが、俺と少女と、死にたがり同士の邂逅だった。
*
次の日、午後から授業を受けた俺は、欠伸混じりに学校を出た。
学内から校門を出てからもしばらくの間、部活の声が辺り一面に響き渡っている。
秋の夕焼けを浴びながら俺は帰路に着く。
赤いランドセルを背負った小学生が、俺を勢いよく追い越していった。
その背中を見つめている俺の脳裏には――ずっと一枚の絵が収まっている。
昨日から頭から離れない光景があった。
昨日から頭から離れない表情があった。
血に染まった少女。
鋭利な視線で俺を睨む少女。
自殺に失敗した少女。
死の結晶をつかみ損ねた少女。
気がつくと、俺はいつもの帰路から外れてしまっていた。
右に曲がらないといけない道を、左に曲がってしまっていた。
その先に何があるのか――
俺は病院へ向かっていた。
*
受付で病室を聞こうにも、俺は少女の名前を知らない。
昨夜(といっても深夜二時頃の出来事だから正確には『今日』であったのだが)、救急車の車内で意識のあった少女は、救急隊員に名前を聞かれていたのだが、かたくなに口を閉ざし、結局名前をかたらなかった。
もしかして、俺に名前を聞かれたくなかったからなのかと、推理してみたが答えは見つかるはずもない。俺は内心で苦笑った。
通りかかった看護師さんに事情を話し、昨夜運び込まれた少女のことを訊ねた。
俺が昨夜通報した者だと告げると、看護師さんは笑顔で病室を教えてくれた。
薬品臭い廊下を渡り少女の病室の前に到着した。
『長崎 志乃』
個室のようであるから、どうやらこれが少女の名前らしい。
ごくりと唾を飲み込んだ。あまり好かれていないことは想像に難くない。緊張の一瞬である。
コンコン、と、ノックをする。
返事はない。
もう一度、コンコン、とノックをしてみた。
誰もいないのだろうか。
もう一度、コンコン、と、ノックすると、
「はい、どうぞ!」
怒った声が聞こえた。凛と透きとおった声は、恐らく昨日の少女のものだった。
昨日とは違って少女の声には力がこもっていた。
どうやら少女は、助かったようである。
内心ほっとしながら、俺は扉を開き中へ入った。
病室には、洗面台とベッド、その傍にはテレビと戸棚があった。
そして、ベッドには病院着姿の少女がいた。
少女の頭には包帯が巻かれ、左手にはギプスをしていた。
傷とか怪我とかに関係なく、相変わらず鋭い少女の視線が俺を貫いていた。
「誰、あなた?」
ぶすっとした表情をしている。
その表情からは確信犯であることが、容易に見て取ることができた。
「誰って……俺のこと忘れたの?」
俺はおどけた声で話し掛けるが、少女の不機嫌そうな顔は変わらない。
もしかしたら、頭を打ったショックなどで記憶が曖昧だったとか、もしくは事故後の後遺症なのかもしれない。
もちろん本気でそんなことを考えたわけではないが、俺は何事にも構わず自己紹介を始めさせてもらった。
「俺は昨日、君の命を救った白馬の――」
「帰って」
速攻だった。
せめて、最後まで聴いて欲しかった。
「俺は――」
「帰って」
「お――」
「帰って」
言い直そうとするも、邪魔されて、しかも次第に切れ味が増していくではないか。
「あなたと話をする気はないわ。だから、帰って」
いっそう冷たく切れ味のある声で、少女は言い放った。
「一応お見舞いってことで来たんだけどさ――」
俺は弁明するが、
「そんなこと私は頼んでいないし、迷惑。早く帰って」
ついに少女は視線すらも俺から外してしまった。
佇むことしかできなかった。
帰れと言われて、このまま帰ってしまっていいものなのか。
しかし、帰れって言われてるんだから仕方がない。このままでは俺は不審者になってしまう。
でも、少しくらい話をしたっていいではないか。
「早く帰って、十秒以内に。じゃないと人を呼ぶわよ」
少女はナースコールのボタンを片手に、こちらを横目で見やった。脅しでないことが表情から見て取れた。
「十――九――八――七――六――五――四――……」
タイムリミットが近づく。
俺は、ぎゅうっと、両手を握りしめた。
仕方のないことだった。
「三――二――いー……」
「……わかったよ」
俺はくるりと回れ右をして、きびすを返した。
そう、仕方ないのだ……。
少女と特に関係があるわけではないし、俺は彼女の手にした死の結晶を粉々に打ち砕いたのだ。
少女が怒るのは無理ないし、もしも俺が逆に少女の立場であったとしたら、きっと俺も同じ態度を取っていたことだろう。観念して、俺は病室を出ることにした。
そして、ドアノブに手を掛けた時だ。
「二度と来ないで」
それは追い討ちだった。
俺は勢いよくドアを開け、後ろ手に扉を閉めた。
思いの他大きな音を立てて、扉が閉じた
なんだよ、あの態度。
俺はやり場のない怒りをずるずると引きずりながら、病院を後にした。
----------(ここまで)----------
拙い文章だ。。。って読み返しながら思いますが、今も拙いことを思い出しました←
精進して参ります。。。
ここまでご覧になっていただき、ありがとうございました。
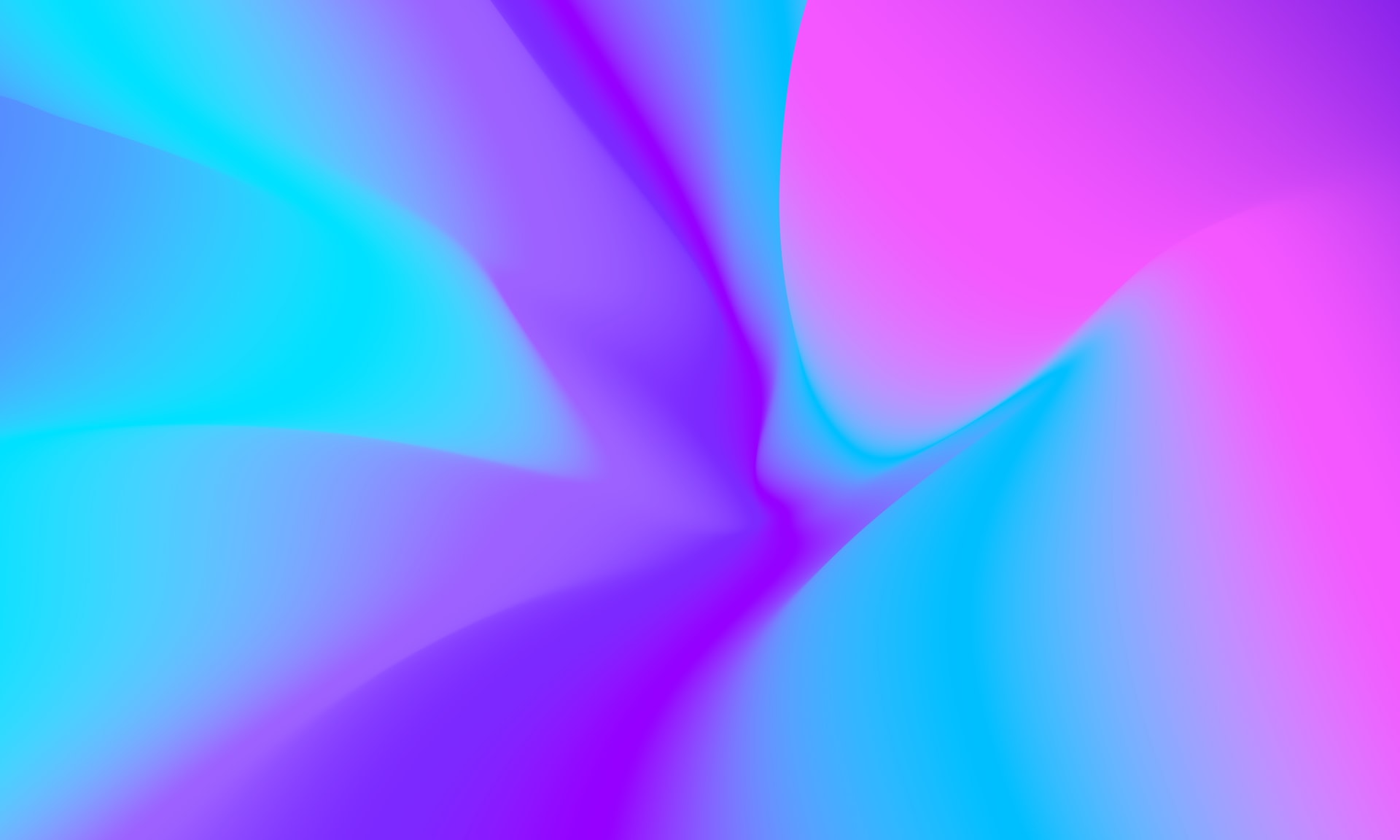

コメント