はぁっと、僕はせっかく溜め込んでおいた夕刻の空気を吐き出した。
幸せを求める謎の女性の登場により、僕のささやかな幸せが奪われてしまうなんて、一分前の自分は考えもしなかった。
そんながっかりした僕の気持ちを知ってか知らずか、目の前の女性はいまも期待に満ちた瞳を向けながら、こちらの出方を窺っていた。
そんな目で見つめられたって、僕からあげられる幸せなんてこれっぽっちもありませんよ。
ビシッと言ってやろうかとも考えたのだが、女性の前では常に紳士的であれ、という僕のポリシーがそれをさせなかった。
「どうしてこれで幸せを受け取れるって思ったんですか」
と、とりあえずは今置かれているこの状況について考察するために、そんな質問をぶつけてみた。
すると女性は、その素敵な笑顔を崩すことなく、
「だって、あなた、履いていないじゃないですか」
そう言いながら、僕の足下を指差した。
「いやいや、靴は履いてましたよ。今はベンチに座ったから、リラックスするために脱いでるだけです」
と、将来的に誰かに質問された際に答えようと用意していた模範回答を、僕は呪文のように唱えたのだが――僕の言い訳を聞いた彼女は長靴を持っていない手で口許を押さえながら、くすくすと笑い出した。
「な、何がおかしいんですか」
彼女の笑いのツボがわからず、僕は動揺して頭を掻いた。自分自身の対応能力のなさに内心呆れていた。
「あなた、知らないんですか」
「何がです」
「有名なんですよ、あなた。この辺りで、夕方になると突然靴を脱ぎだして、噴水あたりまでうろうろしている不審者がいるって」
彼女から浴びせられた言葉に、僕は顔が真っ赤になるのが鏡を見なくてもわかった。夕陽のせいなんかじゃない。頭がカッと熱くなる。
「そうですか、すみません」
僕はベンチの上に横向きに置いてたスニーカーを片方ずつ履き始める。
つまり、僕は不審者呼ばわりされていて、この目の前の女性は僕をからかうために声を掛けただけなのだ。今度は目頭が熱くなってきた。
「え、あの、どうされました」
さっきまで顔を綻ばせていた女性は、ベンチに座り直し靴を履き始めた僕を見て驚いた表情を浮かべ、声を掛けてきた。
「どうもこうも、帰る準備をしているだけですよ」
靴を履くことだけに集中するよう自分に言い聞かせながら、なるべく女性の顔を見ないようにしていた。恥ずかしくて恥ずかしくて、目と目が合ったら泣き出してしまいそうだ。
「そんな、まだ明るいですよ、ほら、見てください」
見てくださいと言われても、顔を上げはしない。上げることができない。涙がこぼれ落ちそうだ。
靴を履き終えると、僕は女性の首より上に視界が上がらないよう注意しながら立ち上がった。彼女の春っぽいワンピースが、僕の醜態を笑っているかのように明るく映えていた。
このままこの場を立ち去ろうとしたのだが、
「待ってください」
と、僕の進路を塞ぐように彼女が目前に立ちはだかった。
「なんですか」
もう僕のことは放っておいてください。
そんな言葉が喉の奥から出掛かっていたのだが、
「これ、持っていってください」
と、再度突き出された黒い長靴を見てしまうと、今すぐにでも飛び立とうとしていた台詞は再び食道を通って胃の中へと帰っていってしまう。
「お願いです、この長靴、受け取ってください」
真剣な彼女の眼差しに射抜かれた僕は、彼女の瞳から視線を逸らすことができなくなってしまっていた。
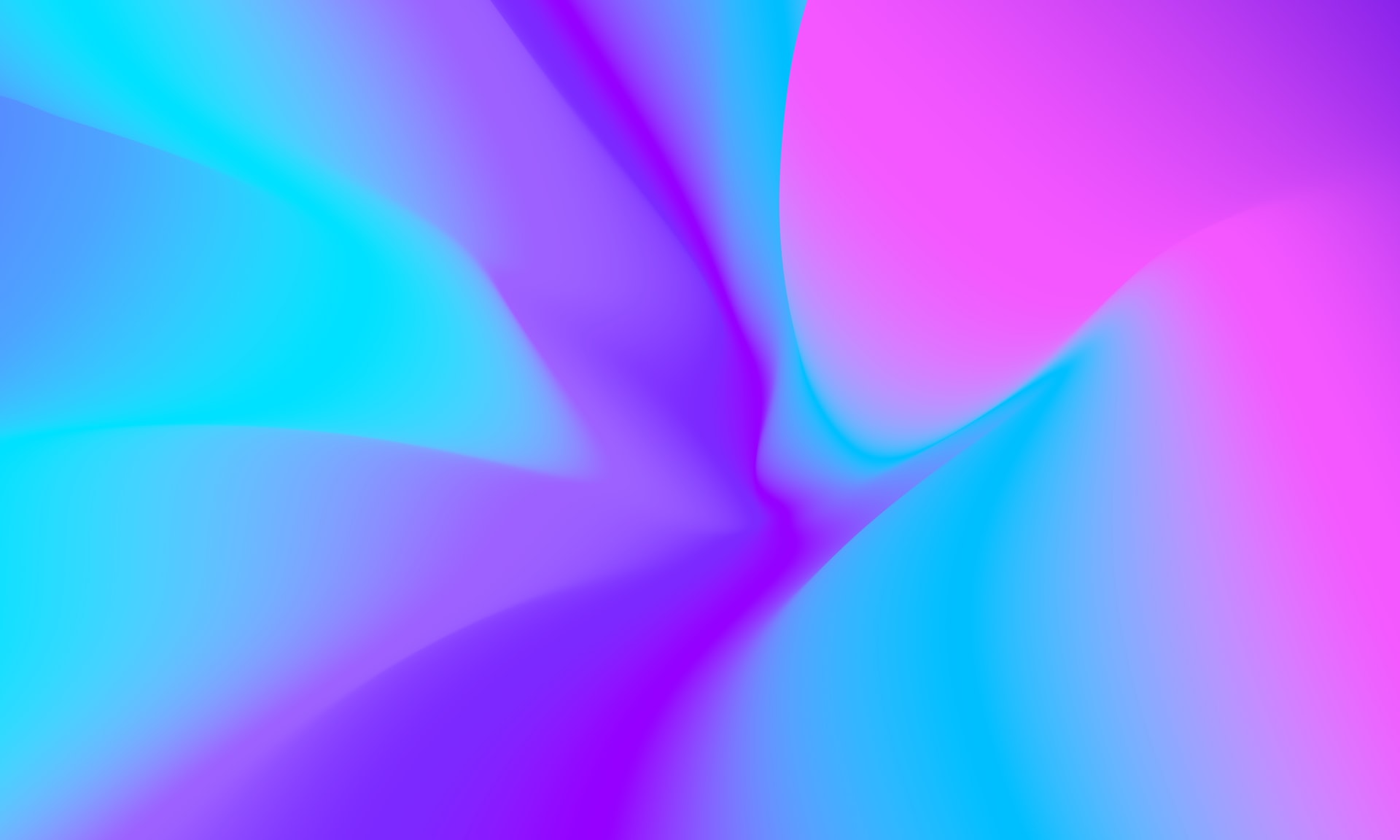

コメント